

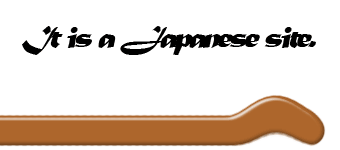
  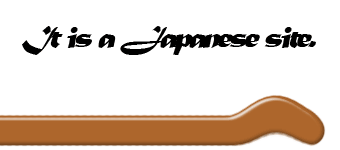 |
| TOP > 初心者講座 > レッスン4 |
| 《 レッスン4 》 麻雀のレベルを疑われる行為
この講座では、最初のうちは、なるべく控える方がいい行為を書いています。 他の講座でも触れている部分や、中には一概に悪いとは言えないものも記しています。 相手をアツクさせ判断を鈍らせる目的や、微差の点差調整など、使われる部分もあります。 『 上家の第一捨て牌のチー 』 【 危険度/低 】 − 個人的な見解 − 手牌状況によってはありえますが、手牌がバラバラの状況でのとりあえずのチーは× 3飜〜満貫確定くらいの手役目標であれば、第一打のチーポンは問題ないかと思います。 また、どうあがいても安手にしかならないけど役がありスピードが見込める場合もOKです。 問題は、どんな形になるかも考えずのチーが×だと思ってもらえれば分かりやすいかと思います。 こういう形で一飜を8回和了るのと、満貫を1回和了るのとでは、どちらが効率いいか考えると 分かるかと思いますが、何でも鳴けば早いなんて考え方は、止めた方がいいしょう。 ただし、時と場合によっては、相手の大物手を潰した時の、相手の精神的なダメージは大きいと言えます。 これは状況判断が出来るようになったら、こういった戦略も含めるといいかと思います。 まずないですが、地和・人和を防ぐ手段でもあります(笑) 『 第一打ドラ切り 』 【 危険度/中 】 − 個人的な見解 − 配牌リャンシャンテン〜イーシャンテンくらいのスピードで打っていけると判断したなら切ってもいいと思います。 問題は、手牌の中で離れた牌だからとか、端牌、字牌という理由だけで切る場合は要勉強です。 ドラへのくっつきにより、形勢の逆転の足がかりや、TOP維持は十分ありえますので。 また、相手にポンされた場合、満貫確定となるわけですから(役+ドラ3枚)、よく考えてから捨ててください。 手役も考えてないのに、そのドラをドラだからでポン・チーする相手は、実力不足と言えなくもないですが… ただし、チーはほとんどがタンヤオ・ホンイツ、逆ではチャンタ系と絞ることが出来るので、やや鳴いた側が不利ですが ポンは場を緊張させる可能性が高いので、そういう意味でわざとポンして(させて)場を緊張させる方法があります。 自分の手はポンしてもバラバラでも、相手(特に上家)はまっすぐには打てなくなるものです。 なので、そういうことも考えてのポンなのか、闇雲なポンなのかは一概に言えません。 雀鬼会ルールでは×です。 『 第一打役牌切り 』 【 危険度/中 】 − 個人的な見解 − 先に言うならば、ドラ表示牌であったり、他家が先に捨てたものなら問題ないかと思います。 スピードテンパイや牌の重なり具合などにより、役牌切りはありえます。問題は、親の連荘を許す“東”切り、 場風牌や三元牌の第一打切りは親の連荘を許す絶好の牌になりかねませんので、よく考えて切ってください。 ※もちろん、毎回あるわけではありません。 考え方として、 字牌というのは、現在の赤牌過多の麻雀において、役牌+赤牌、役牌+ドラという組み合わせは、 気軽かつ有効的な戦法です。 自分の手牌は進んでいないのに、相手にポンされることは、相手だけが少しだけ有利になるということです。 しかし、持ち続けていれば相手に1枚しかなかった字牌が2枚になるかもしれない… となると、 「相手に字牌が入ってポンされる前に先に切る」という考え方も出来ます。 「偶然相手が字牌を持っている可能性があるから切らない」 という考え方も出来ますが、 個人的には 「偶然持っている」 の方が怖いと考えています。 また、数巡後に自分が、その字牌をツモってくるかもしれないという淡い期待も入っています。 役牌をポンされて、相手だけ先行させるのか、自分の手の内をある程度進めて勝負出来る状態で 相手にポンさせるのか…これは、微妙に難しい部分です。相手のテンパイに振り込む可能性もあるからです。 なので切るタイミングを自分で固定するといいかもしれません。自分の場合、手の進み具合を見て6〜8巡目です。 自分が親の場合、北なら早めに切ってみるのは面白いかもしれません。 北家がポンならツモが増えますし、他家がポンなら客風牌がらみで手役が限定されるからです。 実際は、どちらが正しいか?という部分では、あいまいな部分の多いところではありますので状況次第です。 でも、勝負事は1牌の重みというものがあり、相手に鳴かれなかったから「安心」というゆるい気持ちは捨てましょう。 それから、気分でここは打つ打たないと決めるのもいいですが、 最初のうちは、毎回あやふやにせず、どちらにするかを決めてしまう方が良いでしょう。 で、何度か繰り返したら、逆もやってみる…で、自分に合っている方を選べばいいでしょう。 ※雀鬼会ルールでは、すべての字牌の第一打切りは×です。 余談ですが個人的な見解では自風牌は良かったと思っていたのですが勘違いだったようです。 『 順子の食い替え 』 【 危険度/低 】 − 個人的な見解 − 234と手牌にあって、345で三色になるからと5が出たところでチーする行為などを言います。 危険度は低いですが、鳴いて三色も、鳴かずのピンフもほぼ互角ですので、 わざわざ手を開いて晒すよりは メンゼンで進める方が強いと言えます。 相手の手が大きいと感じた時、選べる牌が、“鳴かなければ13枚、1回鳴けば10枚、 2回鳴けば7枚”ということを考えると、守備面に大きな差も出ます。 ただし、相手の大物手を蹴る場合や、リーチの一発消しなど、利用価値がまったくないわけではありません。 こちらも鳴くことで役を確定させておき、攻め相手の捨て牌を討ち取る技術はあります。 でも、やはり場も見れないうちに、運良く出してくれたら…くらいの気持ちで狙う方法ではありません。 これに関しては、個人差があり、和了りやすさ優先と考えてください。 鳴いていく方が安全で、安くても相手の大物手を潰せる場合は、この打ち方もありえます。 鳴いたはいいが、手の内危険牌だらけ…というような考えない鳴きは微妙すぎますので注意です(笑) また、手が安い時は引きも考え、大きく育つ時は攻める。このバランス感覚も大切な要素です。 『 鳴いた牌と同じ牌を捨てる行為(※ポン・チー直後の捨て牌) 』 【 危険度/低 】 − 個人的な見解 − これは食い替えの中でも「現物食い買え」といって区別されています。 過去には、この行為はルール上不可だったはずなのですが、現在はOKなところが多いです。 相手リーチの一発を消したり、鳴いている状態で赤牌5が出た時、完成しているメンツを晒して ノーマルな「5」の牌を切るという打ち方もあります。すぐに切れば安全牌ですしね。 また、 ツイている他家の山牌を引き寄せたり(気持ち上)といった使い方が出来ます。 結果良ければすべて良しですが、自分の手を狭めることには違いありません。 昔からの打ち手には、微妙な行為に写りますが、まったく使えないわけではありません。 むしろ、ルール上OKの場合は、強力な戦術にも変わったりします。 ただ知らずに光ったからボタンを押した…ということがないよう注意してください。 鳴いてみたら、役がなくなった〜が一番困りものですから(笑) 『 無意味な大明槓(手に3枚ある牌を相手が捨てたからと"カン"する行為) 』 【 危険度/大 】 − 個人的な見解 − 通常は3枚あれば形となる暗刻を、和了り点数を安くして(符は上がるが)、相手に手牌を晒して、 カンドラを増やしたいだけの行為は、いくらリンシャン牌が欲しい、運よくカンドラを乗せたいなどの理由があっても×です。 一番最悪なのは、他家がリーチをかけている状態の大明槓をする行為です。 他家3人にカンドラ&カン裏ドラまでも期待させ、自分の手は狭めリーチの権利も失う、 そんな確率も効率も考えない行動が毎回プラスになるとは到底思えません。 捨て牌として通ったのだから、手牌にあるその3枚は比較的安全牌ということです、有効に考えましょう。 また、暗刻で手の中で納めることでリーチ権利も残ります。鳴きを入れている場合は、大明槓することで 逃げられるはずの手が振り込みになることも十分にありますので考えて行動するべきだと思います。 聴牌であれば、嶺上開花を狙えるので良さそうなものですが、引いた牌が危険牌になる率も高いものです。 どうしてもしなければならない状況であるなら、待ちの枚数が多い場合はありかもしれません。 大明槓した本人に対しては不利益の多い行為ですが、2着3着が 独走のTOP者を逆転するための手段としては 面白い手ではあります。 ようは計算ずくでの他家へのアシストという使い方です。 これで、独走TOPが更に独走する可能性は無きにしもあらずですが… それから、自分が聴牌していて相手のリーチ同巡内で捨て牌をカンし、 相手の一発を消しながらリンシャン牌でテンパイやツモを狙う方法はあります。 わざわざ晒すのであれば、それなりの理由付けがあれば迷惑とは言いません。 逆に、他家も大明槓した他家の聴牌も意識する必要もありますね。 ただ、三飜にも満たない手役状況であれば、考えて大明槓する方がいいとは思います。 それからもうひとつ、自分の手が大きい(または小さい)と相手に思わせる使い方です。 いつもは、「カン」をやらない人がいきなり 「カン」 と発生したら、警戒しませんか? ようは、いつもこればかりを繰り返すのではなく、スパイスとして使うというやり方は 相手の心境を変化させ、オリさせたり、フリコミをさせたりと、強力な戦術へと進化します。 『 他家リーチに対して、無意味な加槓(ポンしてる牌をツモり明槓する行為) 』 【 危険度/大 】 − 個人的な見解 − 数牌である場合の 「カン」 は、槍槓で相手の和了り役を1飜増やしてしまう可能性があります。 字牌の4枚目の場合は、国士無双以外に安全な牌です。 なので、相手にリーチがかかっていたり、大物手の可能性のある捨て牌だった場合は、 素直にそのツモった牌を捨てるのが技術というものです。 また、他家にリーチがかかっていない場合でも、加槓は不利な状況を作る可能性の方が高いです。 槍槓(チャンカン)の可能性と、危険牌を引いてくる可能性も考えなければいけません。 相手にカンドラ&カン裏ドラを期待させ、自分の手は狭め、振込み率を高くする、 そんな確率も効率も考えない行動が毎回プラスになるとは到底思えません。 中にはそれにスリルを感じるのが好きという人もいますが、技術アップには不要です(笑) 上の大明槓よりも、さすがに評価は出来ませんし、加槓(カカン)した本人にメリットはほとんどありませんが TOP目以外の人にアシストする形になれば、 案外面白いかもしれません。 これによって、TOPの調子が崩れれば万々歳なのですから。…でも、やはりあくまでスパイスです。 自分にカンドラを乗せようとするためだけの加槓は…聴牌してるならありかな…嶺上開花でツモれる可能性が ちょこっとだけあるから…ま、どちらにしてもサーカスプレイですけどね。 微差でトップの場合、加槓で符ハネすれば逆転の手に育つ場合や、 イーシャンテンからテンパイになる確率の高い手牌、またリンシャンツモで逆転である場合、 ポン後に狙いが逸れた手牌になってしまった場合、加槓は有効な場合もあります。 『 役満を確定させる可能性のある捨て牌 』 【 危険度/特大 】 − 個人的な見解 − 三元牌の2鳴きをしている場に、まだ鳴かれていない最後の三元牌を捨てて鳴かれ役満であると確定させた人。 四風牌の3鳴きをしている場に、まだ鳴かれていない最後の四風牌を捨てて鳴かれ役満であると確定させた人。 上の二つはパオ(包)と言って、役満を確定させた相手にペナルティがあります。また、ペナルティはないですが 他にも、緑一色 や 清老頭 といった鳴きにより役満を完成させる可能性のある時の捨て牌も注意が必要です。 もちろん、同牌が3枚切れている状況や、自分で3枚持っている状況なら捨てても問題ありません。 また、序盤であれば捨てる行動もありです。そこまで揃っている状況だった場合、コンピュータゲームであればゲーム性、 リアルであれば、ツキやイカサマしかありませんので、自分の手牌が早そうであれば、攻めもあります。 でも、中盤以降に掴まされているのであれば、相手がその待ちでないとしても押さえ(引き)ましょう。 唯一の例外は、相手と同じように役満(数え含む)を狙える場合のみです。 それでも、振込み率と浪漫を天秤にかけたら、どちらを取るかは本人のスタイル次第ですが… もし、これがどうして悪いんだろう?と思われる場合、 麻雀は一人でやっているわけではないことを考えるべきところです。 こういった考えのない捨て牌が、せっかく4人で囲んだ卓を面白くない麻雀にしてしまうのです。 と同時に、卓を囲んでいる相手に対し、そんな捨て牌に巻き込まれる相手の気持ちも分かる必要があります。 ツモられれば均等に引かれるので(親は倍ですが)、誰かがマイナスにならない限り、まだ逆転の可能性も残りますが 振り込んだせいで、ハコワレとなってしまえば終了となって、逆転の可能性も失います。 圧倒的不利な状況であっても、逆転の可能性があるのが麻雀の楽しさでもありますよね^^b 初心者のうちは分からずに捨てちゃう人もいるのは分かりますし、 それでも勝負だったんだから仕方がないというのも分かります。 起こってしまったら、それはそれで仕方のないことです。 技術の中には、 相手の手牌を読みきった上で、ポンさせ、相手の捨て牌で和了る技術はあります。 また、勝負として均衡の取れた鳴かせであれば、それはそれでありとも考えてはいます。 『 染め手に対するアシスト(相手の鳴きや河を見ていない捨て方) 』 【 危険度/中 】 − 個人的な見解 − この行為はレベルの高い人も行う戦法のひとつなので、一概に悪いとはいいませんが 相手の手牌状況や、捨て牌状況を読んでいない方がやるのは×です。 相手に3回鳴かれても、こちらがテンパイ出来る確率が高いなら、 わざと鳴かせて相手の手牌を狭めさせるという戦法は、高等技術になります。 逆にテンパイ出来ないような無理なツッパリなら、場を良く見て麻雀しましょう。 もちろん、2回鳴かせても十分に間に合う手牌だから捨てたのなら立派な打ち筋です。 『 親のリーチに対する北家のアシスト(北家のポン・カン) 』 【 危険度/大 】 − 個人的な見解 − 通常は、親がリーチをしていてもしていなくても、北家が親の捨て牌を鳴き、親のツモを早める行為は 迷惑レベルが高いのですが、親がリーチをしているタイミングで鳴くというのは、 ただのリーチの場合であっても ツモで1飜増やして しまう確率をもっと増やしてしまう行為です。 (一発は消えますが…) 親がツモ→捨て牌→北家がポン→捨て牌→親がツモということは、南家・西家・北家ともツモしておらず、 ※この親のツモを早める状況を「親のツモを増やす」と言います。 その場での些細な親の連続ツモですが、麻雀において1巡というのは結構重要な場合も多いものです。 北家がその一回の鳴きでテンパイをする形であるなら許される場合も多いですが たいていがムリ鳴き、または、1000点和了りのための鳴き(場面による)が多く、 この行為で親の連荘を許してしまっては、 南家・西家への迷惑以外の なにものでもありません。 ただし、場の状況を読めるようになってきたならば、北家で手牌の形を良くするためであれば、 親の捨て牌をポンすることもありになってくるとは思います。 もちろん、オーラスで逆転可能状態であったり、手が大きく育ちそうな場合、 早くてTOP維持出来そうな場合、他家においおいと思われても鳴く手はあります。 失敗しても親が連荘すれば、次に和了れる可能性も出てきますからね。 『ラス確定和了り(4位ラス確定和了り)/確定オーラス和了り/アガラス(和了りラス)など』 【 危険度/小 】 − 個人的な見解 − オーラス4位者は和了るなというわけではありません。 よく見かけるのが、4位者が役牌を鳴き、役牌のみで終わらせる行為や、 ダマで「ロン・ピンフ」で4位者が4位で終わらせてしまう状態を良しとしないということです。 個人的には手牌の進み具合にもよるとは思いますが、 やはり、4位者であっても、ひとつでも順位を上げる工夫は考える方がいいわけです。 もちろん、4位の人が和了ってはいけないということではありませんし、そういうルールもないです。 ただ、最低でも3位に逆転出来る可能性を秘めた手作りをして和了りに向かうことが重要なのです。 これにより、TOPに対して3人の敵がいるという図式になります。 例えば、8000点をTOP者が4位者にロンされることで暫定2位者に逆転されるという場面もありますよね? また、失点を減らす努力にもつながります。 勝負が終わる最後の最後まで、お互いの意思の有無関係なしで、 緊張感のある勝負になっている方が麻雀は面白いものです。 (プロのリーグ戦などは、小さな点差が響くためにラス確をやる場合もありますが それは区切りのある長期的な結果を見て和了るというものですので、一般の対局とは違います。) もちろん、仕方のない場面というもの存在します。 個人的な見解ですが、なぜ東風戦の東四局と、半荘戦の南四局を わざわざ「オーラス」という別名を付けたのでしょう。 最後の勝負、勝っても負けても良い勝負をしましょうという暗黙の了解があるように感じます。 そんなわけで精神的な部分もありますので、人によっては難しいところもありますね。 ここでさっさと終わらせれば、次は勝てるかもしれないと…この軽い気持ちも分からなくもない。 麻雀も、将棋や囲碁のような勝ち負けを競いあう部分はあるわけで、負けている者が そういう逃げの気持ちで打ってるということは、結局、運の良い時だけ勝ちゃいいんだで終わっています。 技術を磨く段階で、そんな気持ちでは、やはり微妙なんですよね。 ただし、例外を上げれば、ひとつは「焼き鳥ルール」付きの対局の場合 焼き鳥を逃れるための4位確定和了りはあるでしょう。 それから、「リーチが入ったオーラス」または「相手に高い聴牌のある可能性のある捨て牌のオーラス」 これは、安くても早和了りをして終わらせる方が被害を少なくする意味では大切です。 これ以上、負けを増やされたり、ツモor放銃で飛ばされるより、被害を最小限にとどめて終わらせたり、 飛ばされずに終わる方が良いのも当たり前のことですので。 ただ、まだこれから技術を磨こうという段階で、負けてるからと、いきなり逃げ思考にならず、 最後まで粘りを付ける体質にはなっておきたいものです。 逆転出来る配牌かツモか、それともまったくダメなのか、これはオーラスもあきらめない気持ちで 何度も打ってみないと分からないものですよね。 『 鳴き麻雀をボヤく / ツカないことをボヤく / 初心者を言葉でいじめる 』 【 危険度/大 】 − 個人的な見解 − ネット麻雀では、相手の顔が見えません。 そのため、片寄った感覚の打ち手や、自分の麻雀がうまいと自意識過剰な人が、 一見格下に見える相手に 行う行為が、 「チャットでボヤいたり」、「初心者をバカにしたり」といった程度の低いことを行う行為だとなります。 一見格下というのがミソで、実際は、たまたま卓が一緒になった相手というのは、レベルが分からないものです。 故意にヘタなフリをすることも上級者にはありますし、また本当に技術が高い人は、打ち方が初心者返りしている こともあるそうなので、実力なんて一概には分かりません。 まして、相手の手牌などわかるはずもなく、どんな形から鳴いたのか、たまたま当たり牌を捨てたのか 分かるはずもないでしょう。ロンは誰でもあることですし。。。 麻雀で鳴きの巧さとは「高等技術」なのです。それを分かっていない相手は、その人こそ格下と思います。 ルール上認められている範囲内での行為は、咎められる意味合いのないことは誰しもが分かるところ。 柔軟性のない相手の中傷と言うのは、どんな言葉でも腹立たしいものですが、やはり仕方ないところでもあります。 麻雀に強くなりたかったら、「相手の行動をボヤかない」「相手をバカにしない」 一人でディプレイの前でボヤく分には無害ですが、チャットのような公の場で言うようになったら最低です。 しかし、だからと言って、度が過ぎた行動で言われた場合は、 言われた方も考えないといけない部分が多分にあるものなんですけどね。 また、これは余談ですが やたらポンチーが入ってツモ番がこない麻雀と言うのは、ホントにつまらない麻雀ですからね^^; ポンチーの多くなる局面と言うのは、結果的に3人麻雀をやっている状態と同じです。 3人麻雀は、雀士の技術レベルより運のいい人優先になりやすいので、 結果4人打ちでやっていてもサンマ(3人麻雀)と なんら変わりはありません。 三人は聴牌が早まり、一人だけ遅れを取る状態だけは、なんとして避けたいものですね。 こういった数々の行為は、麻雀をやっていて相手が不特定多数の場合、ちょくちょく見かけることです。 これらは、デジタルでもオカルトでも、その他いろいろな戦略が麻雀にはありますが、 戦略でもなんでもない、麻雀という物事を知らない人のやる行為とも言えます。 技術レベルが上がっていき、計算してこういう行動が出来るレベルになったなら問題ないですが… 何かリスクで、何が正解か、というのは、麻雀では微妙な部分が多いです。 知らずにやる行為や、 頭では分かっていてやる行為 と、 リスクを経験した上でやる行為では、やはり同じ行動でも違うものです。 麻雀の技術というのは、極力運の要素を減らし、その中で勝つことが麻雀の技術です。 また、たまたま運のなかった卓で、逆転のために運要素を吊り上げるのも技術の一つです。 ある程度技術やリスクを知った上で、こういう行動の成果を研究したり、リスクを知ったり これは重要ではあります。その場かぎりの運が良ければ…とは違うわけです。 麻雀の技術向上のためにいろいろやってみるというのは、ネット麻雀では気軽に出来る反面 「これでいいや」程度で考えて、ちっとも向上心のない打ち方を繰り返す人もいます。 自分の技術レベルを知り、相手への危険レベルを知り、そこから一歩進んだ考え方をする… 「ここで確率は低いけど、和了れれば、符が上がって逆転出来る “カン” 」 この感覚と、 「楽しいから場を荒らしてやれ “カン” 」 とか 「自分が好きだからやるんだ “カン” 」 との感覚の違いって分かりますよね? たまたま、カンした時のカンドラの乗った喜びや、 リーチした相手の牌を無理ポンしたら、 リーチした相手が次の捨て牌で捨てて、 それをロン出来たとか、 偶然、確率の低いことが起きた時、 うれしくなることもあるでしょう。 確かに、その行為がいつでも起こりえ、また正確な打ち筋なら問題もないのですが… 確率的にも行動的にも不利になる行為は、勝てるチャンスを自ら減らしているだけのこと。 これやってても勝てるからやるんだ!…という人は、よほど運が強い人なんでしょう。 もちろん、やってはいけないわけではありません。ルール上は問題ないのです。 それが、その人のレベルであると相手が感じるだけのことなのですから。 たしかに麻雀そのものは、「 勝ち負けは運、その過程は技術 」 だと思います。 技術がアップすれば、無駄な振込みは減り、技術で勝てる回数が増えるわけです。 それが気持ちいいと感じるか否かは、個人個人の麻雀の捉え方ということになります。 − 以 上 − 思い出したり、気が付いたり、どこかで情報を仕入れたりしたら、またいろいろと追加していく予定です。 |
【 覚えるべき手役 】 ← ・ → 【 何を残すか 】 |
TOP > 初心者講座 > レッスン4 |
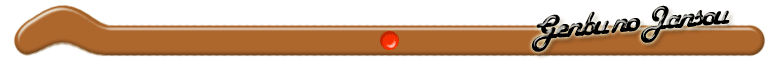 |